中小企業にとってスキャナ保存制度は使える制度なのか?
トレージの大容量化・低コスト化等に伴い、日々の業務活動によって生じた膨大な請求書・領収書といった書類について、場所を取らない電子データとして保存しておきたいというニーズが高まっているようです。電子データ化に当たっては、税務上の帳簿書類保存義務を満たすかということが必須の検討事項となりますので、国税関係書類のスキャナ保存制度の適用を受けるための要件を見ながら、中小企業の視点からスキャナ保存制度利用の是非について考えてみます。
まず、現在の利用状況はスキャナ保存の申請に関する承認状況を見れば一目瞭然です。
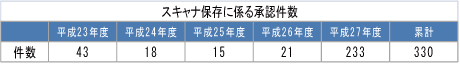
出典:「税務統計」https://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/sonota2015/pdf/H27_denshichobo.pdf
日本の法人数が約260万社ある中で、平成27年度迄にわずか330件(申告所得税の承認も含まれるので法人についてはこれ以下)しかスキャナ保存についての承認を受けていません。平成27年度に承認が増えているのは、対象となる契約書・領収書に係る金額基準(3万円未満)の廃止、スキャナ読み取り者の電子署名が不要等の要件緩和があったため大企業の一部が新たに承認を受けたもので、中小企業で承認を受けているところはほとんどないと思われます。また、平成28年度にもスマートフォンでの読み取りが可能となる等更なる要件緩和がされましたが、現状では大きな傾向は変わらないと予想します。
では、スキャナ保存の拡大にとって何がネックとなっているかというと、コスト負担を要するという点で主に次の二つの要件が挙げられると思います。
ネックとなる要件①:タイムスタンプの付与
電子化したデータに一般財団法人日本データ通信協会の認定を受けた事業者の提供するタイムスタンプを押す必要があります。平成28年11月29日現在で認定を受けている事業者は6社しかなく、ある事業者を参考にすると最低ロットでも年間10万円~、無制限の定額制ですと年間数百万円といった単位で費用がかかるようです。
ネックとなる要件②:検索機能の確保
電子化したデータの記載事項について、次のような検索をできるようにする必要があるとされています。
(1)取引年月日その他の日付、取引金額その他の主要な記録項目での検索
(2)日付または金額に係る記載項目について範囲を指定しての検索
(3)2以上の任意の記載項目を組み合わせての検索
こうした検索を可能にするためには、単に書面をスキャナで電子化するだけにとどまらず、記載された内容を日付・金額といった項目毎に記録し、データベース化する必要があります。これは単純にスキャナで読み取った書面をOCR認識して保存するだけでは現状難しく、自社でシステム構築をすることが難しい中小企業では、ベンダーが提供するサービスを利用する等の必要がありそうです。
他にも規程・体制の整備や書類を受領後電子データとするまでの期間の制限等スキャナ保存をするためには満たすべき要件がいくつかありますが、コスト負担が中小企業にとっては一番の大きなハードルでしょう。今後、技術の進展や競争の促進によって、領収書・請求書の読み取りによって会計仕訳の自動作成、仕訳データとPDF化したデータの紐づけ、自動的タイムスタンプ付与等迄を一気通貫したサービスが安価に登場することを期待したいです。
過去のUAPレポート
- レポート検索

