外国子会社合算制度の見直し 対象地域は全世界へ
内国法人が50%超を直接及び間接に保有する子会社を外国に設立した場合、その外国における租税負担割合が20%未満で、かつ、適用除外要件を満たさない場合には、子会社の所得は親会社である内国法人の所得に合算され、日本の法人税が課税されることになります。また、適用除外要件を満たした場合であっても、資産性所得に該当するものは合算課税の対象となります。そこで、子会社の所得が合算課税の対象とならないようにするために、租税負担割合が20%以上の国や自治体に子会社を設立するのが一般的です。
ただ、近年ヨーロッパ諸国を中心に、課税ベースを拡大し、法人税率を引き下げる改革が進められているため、子会社設立後に租税負担割合が20%未満となってしまう場合があります。
この場合に、最も単純に合算課税を回避するには、租税負担割合が20%以上となる国や自治体に子会社の本店を移転する方法があります。
ところが、今後は本店移転による合算課税回避が出来なくなる見込みです。というのも、平成29年度の税制改正で、合算課税の対象判定を、現行の租税負担税率の判定から、子会社の所得の種類に応じた判定への改正が見込まれているからです。
具体的には、下記図表のとおり、租税負担税率が20%以上であったとしても、経済実体がない受動的所得に該当するものは、合算課税の対象となり、一方で、租税負担税率が20%未満であったとしても、能動的所得に該当するものは、合算課税の対象にはならないということです。
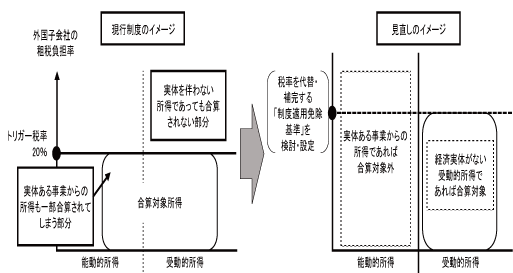
※能動的所得:子会社が自らの能力と責任を持って取り組む商品の製造・販売やサービスの提供による対価の獲得等、経済実体がある事業から得た所得
※経済実体がない受動的所得:一定の金融所得や実質的活動のない事業から得られる所得等
なお、改正によって、世界中に設立されている全ての子会社の受動的所得が合算課税の対象となると、過度の事務負担が生じるため、税率を代替・補完する「制度適用免除基準」の導入が検討・設置されるようです。現段階では、能動的所得及び経済実体がない受動的所得の範囲も明確ではないため、子会社のどの所得が合算課税の対象に該当するかどうかは、改正の具体的な内容次第ですが、税務メリットを考慮して、子会社の設立地域を検討する時代は幕を閉じたようです。
過去のUAPレポート
- レポート検索

