自己建設高額特定資産と建設仮勘定
消費税においては、中小事業者の事務負担に配慮する観点から、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務を免除する「事業者免税点制度」が設けられています。その事業者免税点制度は毎年のように改正が行われ、その事業者が消費税の課税事業者か免税事業者かどうかの判断事項が年々増えています。
平成28年度税制改正においても事業者免税点制度について改正が入っています。制度概要、適用時期及び用語の意味は紙面の都合上、ここでの記載は省略します。詳細は、国税庁の資料(消費税法改正のお知らせ※1)をご覧ください。
今回の記事で焦点を当てるのは、自己建設高額特定資産を建設した場合の事業者免税点制度の適用制限についてです。自己建設高額特定資産を建設した場合には、「自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合」に該当することとなった課税期間の翌課税期間からその建設が完了した課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで事業者免税点制度を適用できないこととされました。
ここで、「自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合」とは、自己建設高額特定資産の建設に要した費用の税抜価額(事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受ける課税期間に行ったものを除きます。)の累計額が1,000万円以上となった場合をいいます。
ところで、建物の建設工事や自社利用のソフトウェア開発を発注した場合には、完成引渡しまでの期間が長期に及ぶことから、完成引渡しまでにかかった発注代金その他経費の額を建設仮勘定として経理処理し、建物又はソフトウェア全部の引渡しを待って固定資産に振り替えることが多いかと思います。
消費税法においては、建設仮勘定として経理した場合でも原則として、物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間においてその都度課税仕入れとして仕入税額控除します。ただし、消費税法基本通達ではその建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、その目的物の完成した日の課税期間において一括して課税仕入れとして仕入税額控除することも認められています。
そこで気になるのが、建設仮勘定として処理した場合にどのタイミングで「自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合」に該当するかです。
この点、「自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合」とは、自己建設高額特定資産の建設に要した費用のうち、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受ける課税期間のものは除かれますので、言い換えると、仕入税額控除を行った費用の累計額が1,000万円以上となった場合、と言えるかと思います。従って、建設仮勘定として処理した費用についていつ仕入税額控除したかで「自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合」に該当するタイミングが変わります。
例えば、次の前提条件をもとに2つのケースを考えてみます。
【前提条件】
1.各課税期間は1年で第X-1期及び第X期の課税売上高は1,000万円以下
2.第X-1期及び第X期は課税事業者に該当(課税事業者・簡易課税は選択していない)
3.自社利用のソフトウェア開発にあたり設計料2,000万円、開発費2,000万円の内訳で事業者に発注し、設計は第X期中に完了(○)、開発は第X+2期に完了し引渡しを受ける(◎)
<ケース①:都度仕入税額控除を行う場合>
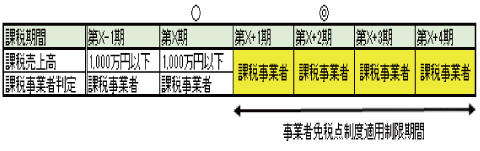
⇒第X期に「自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合」に該当し、第X+1期は事業者免税点制度適用制限を受け課税事業者となります。
⇒ソフトウェアが完成する第X+2期以降3年間についても同様に制限を受け課税事業者となります。
<ケース②:一括して仕入税額控除を行う場合>
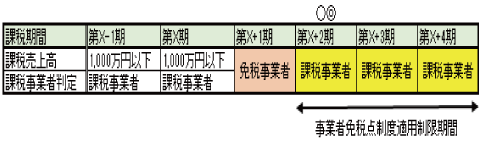
⇒第X+2期に「自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合」に該当するとともにソフトウェアの引渡しを受け、第X+2期以降3年間について事業者免税点制度の適用制限により課税事業者となります。
⇒第X+1期は事業者免税点制度の適用制限を受けず、基準期間(第X-1期)の課税売上高が1,000万円以下であることから免税事業者となります。
設備投資として自社の基幹システムを刷新する場合には、完成するまでいくつかの工程があり、その工期も長期になり複数の課税期間を跨ぐことがあります。記載ケースの通り建設仮勘定の経理処理によって「自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合」に該当するタイミングが変わることもあります。従って、資金繰りや事業計画で納税額を試算する場合には経理処理による違いを想定するのも良いかもしれません。

※1 国税庁:消費税法改正のお知らせ
(Ⅳ 高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し
過去のUAPレポート
- レポート検索

