会社法改正後のキャッシュ・アウト制度の選択~特別支配株主の株式等売渡請求の創設~
株式が分散している多くの中小企業にとって、支配株主の議決権比率を高めるために必要な株式の集中は頭の痛い問題です。支配株主への売却に素直に応じてもらえれば結構なのですが、売る、売らないでトラブルになることもよく見られます。解決策として、少数株主の意向にとらわれず、その保有する株式を強制的に支配株主や発行会社に売却させることができる手段を検討することが行われます。
会社法では大きく2つの方向でそのニーズに応えています。1つは支配株主等への株式の売渡しの強制を認めることであり、もう1つは端株にしたあと発行会社への強制売渡しを認めることです。
改正前会社法における主たる制度として、前者には①相続人等に対する株式売渡請求制度、②現金合併、③現金株式交換、④取得条項付株式があり、後者には⑤株式併合、⑥全部取得条項付種類株式があります。
ところが、①の相続人等に対する売渡請求制度は、相続発生という不確定な時期にしか使えず株式集中までに時間がかかること、少数株主によるクーデターのリスクが少なからずあること(UAPレポート参照)から使い勝手がよくありませんし、②現金合併と③現金株式交換は非適格再編に該当し相当な課税が生ずることからほとんど利用されていません。また、④の取得条項付株式にはそもそも既存株主全員の同意が必要なのでトラブルが予想されるときには利用できません。さらに、⑤株式併合には反対株主の株式買取請求権が認められておらず、強行すると株主総会決議が取り消されるリスクがあります。
そのため、現在実務で一般的に利用されているのが⑥全部取得条項付種類株式です。これは、会社が全部取得条項付種類株式の取得をした上で、少数株主の有する株式をいったん端株にした後、その端株を会社が現金で少数株主から取得する(端数処理)ことにより、支配株主に議決権を集中させるという仕組みです。
このような状況の下、平成26年の会社法の改正により、⑤の株式併合に反対株主の買取請求権が認められ、さらに、⑦特別支配株主の株式等売渡請求制度が創設されました。
この⑦の新制度では、特別支配株主(=議決権の90%以上を有する株主)が、株主総会を開くことなく、取締役会の承認により、少数株主全員に対して所有する株式の全部を自分に売り渡すことを請求することができます。
改正後の実務では、⑤株式併合、⑥全部取得条項付種類株式、⑦特別支配株主の株式等売渡請求のいずれかが活用されることになると予想されますが、何に着目して選択すればいいのでしょうか。制度の使い勝手につき簡単に比較してみます。
まずポイントとなるのは、実行するのに必要な議決権数です。⑤株式併合と⑥全部取得条項付種類株式は株主総会の特別決議が必要とされるため、他の株主との合意などにより2/3以上の賛成票を得なければなりませんが、⑦特別支配株主株式等売渡請求では株主総会は不要であるものの、特別支配株主であるために90%以上の議決権を所有していなくてはなりません。90%の判定上、他が保有する株式のどこまで含めて判定できるか否かは、将来の法務省令で定められることになりますが、現在の議論状況では、おそらく支配株主である個人1人(+その100%所有等法人)だけで判定することになると思われます。
次に機関決定については、株主総会の特別決議が、⑤株式併合では1回、⑥全部取得条項付種類株式では定款変更時とその取得時にそれぞれ1回必要で、時間とコストがかかります。他方、⑦特別支配株主の株式等売渡請求では取締役会の承認だけで実行できます。
また、⑤株式併合と⑥全部取得条項付種類株式では、端株について端数処理が必要となり面倒ですが、⑦特別支配株主の株式等売渡請求ではそれが不要です。
なお、中小企業にはあまり関係ありませんが、発行済みの新株予約権を同時に強制的に取得するためには、⑦特別支配株主の株式等売渡請求を利用するしか方法がありません。
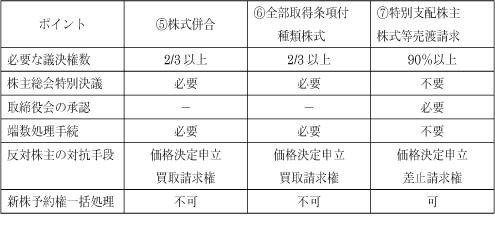
また、法務だけでなく税務も気になるところです。
現在のところ、⑦特別支配株主の株式等売渡請求についての課税上の取扱いについて公表されたものはありません。しかし⑦の新制度では、株式を株主間で譲渡するだけなので、⑤株式併合と⑥全部取得条項付種類株式と同様、株式を手放して現金化した株主に譲渡損益課税だけが行われることになるよう整理されることが予想されます。そうすると、課税上の取扱いではいずれを選択しても特段有利不利がないことになります。
結局、中小企業の事業承継対策に用いる場合、議決権数が90%以上あれば、時間もコストもかからない⑦特別支配株主の株式等売渡請求を選択し、90%以上なければ既存の⑥全部取得条項付種類株式に加えて⑤の株式併合を選択することが多くなると思われます。
なお、創設された特別支配株主の株式等売渡請求については、買取対価を確実に支払わせることが制度的にできていないのではないか、取締役の善管注意義務違反につき株主代表訴訟が提起されるリスクがあるのではないか、などの懸念があります。実務で活用するには事前に慎重に検討すべきであり、今後の動向に注意が必要です。
過去のUAPレポート
- レポート検索

