建物と建物附属設備を区分して償却費アップ!~工事見積書がなくても可能な方法~
法人やアパート経営を行う個人が建物を購入した場合には、早期に償却費を多く取るために、建物本体と建物附属設備とに区分して減価償却計算を行うことを、まず考えるのではないでしょうか。しかし中古物件を取得した場合には、新築当初の工事見積書を建築会社や売主から入手できないことが普通です。当然、根拠資料が無ければ、区分することはできません。その場合どうしたら良いでしょうか。
一つの方法として、市役所の固定資産税課で再建築費評点数算出表という固定資産税評価の計算資料を入手して、その評価額で按分するという方法があります※1。再建築費評点数算出表では、建物が躯体、床、間仕切、天井、屋根、建具、建築設備(給排水設備・配線設備・照明設備)などに細かく区分して評価されていますので、建物本体部分と建物附属設備部分とに区分・集計することで、取得価額の区分割合を算定することが可能となります。この方法は、名古屋国税不服審判所が平成13年2月19日付裁決で、「合理的な方法」の1手法であると認定している根拠ある方法です。こうして計算した区分割合は新築時の区分割合ですから、中古建物につき築年数に対応した補正をする必要があります。この補正で、建物附属設備は建物本体よりも耐用年数が短いですから、築年数を経過すればするほど、建物附属設備の割合は減少します。ですから、築浅のほうがこの区分計上する効果が高いと言えます。下記設例で、区分しない場合と区分した場合の5年間の償却費合計額を比較してみます。
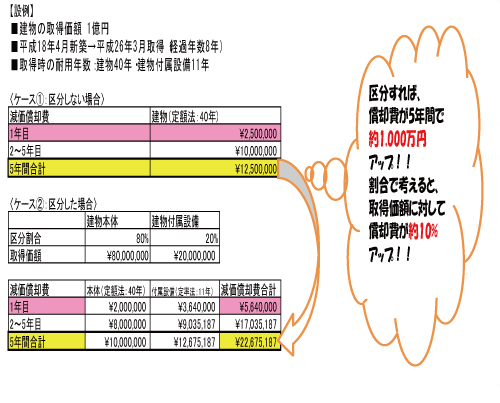
区分した場合は区分しなかった場合と比べて5年間の償却費合計が取得価額の10%分増加しています。どちらの場合でも40年間トータルの償却費合計額は同じですが、早めに償却して直近の納税負担を減らしたい意向がある場合には、是非検討してみてはいかがでしょうか。

※1 再建築費評点数算出表については、東京都23区内の所有物件であれば、管轄の都税事務所の窓口にてその写しを取得することができます。但し、古い建物は再建築費評点数算出表が廃棄されていて、保管されていないケースもありますので、事前に管轄の都税事務所に確認する必要があります。
過去のUAPレポート
- レポート検索

