小規模宅地等の特例改正による中小同族法人オーナーへの大きな影響
平成25年度税制改正により、小規模宅地等の特例が改正され、特定居住用宅地等の限度面積が240㎡から330㎡に拡大されました。改正後の適用対象となる減額割合と限度面積は下記の表のようになります。
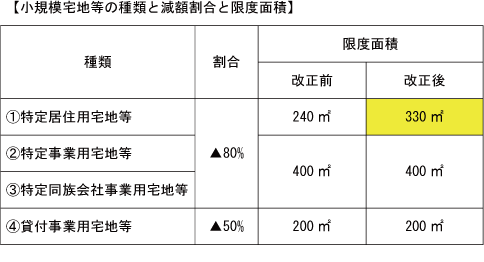
さらに、居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積が拡大される有利な改正がなされます。改正前では、①特定居住用の240㎡と②③特定事業用の400㎡とは、その合計で最大400㎡になるまで「限定」併用※1できるのですが、改正後は、「完全」併用が認められ、最大で730㎡(①の330㎡と②③の400㎡の合計)までこの特例の適用が可能となります※2。
「完全」併用の恩恵をフルに受けられる主な人は、自分の土地を自社に貸し付けている中小同族会社のオーナーだと思われます。③特定同族会社事業用宅地等とは、オーナーとその親族等で発行済株式総数の50%超を保有している同族法人の事業(貸付事業を除きます。)の用に供されていた宅地等で、法人役員要件と保有継続要件を満たすものをいいますので、同族会社に個人の土地を貸して事業をしているケースの多くが③に該当します。そうすると、自宅の他に自社への貸付地を所有しているオーナーは、今までは二つ合わせて、最大400㎡までしか特例が使えなかったものが、今後は、自宅で最大330㎡、自社貸付地で最大400㎡まで、それぞれ特例の適用が可能になりますから、使い勝手が大幅に良くなったことになります。
その際事前に確認したいのが、オーナー個人と同族会社との契約関係です。高額な借地権課税(入口課税)を避けるため、オーナー所有の土地を同族会社に貸すときは、(ア)使用貸借契約(タダ)にして土地の無償返還の届出書を提出するか、(イ)賃貸借契約にして土地の無償返還の届出書を提出しているかのどちらかによることが一般です。
注意したいのは、この特例の対象となる不動産の貸付けは相当の対価を得て継続的に行うものに限られているということです。よって、(ア)の使用貸借により貸し付けられている宅地等は、減額特例の対象になりません。他方、(イ)の賃貸借の場合には、一定の要件を満たせば③の特定同族会社事業用宅地に該当します。
さらに、同族法人へ土地を貸している場合には、自社株評価との関連も重要です。(ア)の使用貸借の場合には、法人に帰属する借地権はありませんから、オーナー個人の土地は自用地として100%評価され、自社株評価への影響はありません。しかし、(イ)の賃貸借の場合には、民法上の借地権は存在し、ある程度の利用制限があることから、20%の評価減がなされ、その20%は自社株評価において借地権として取り込まれます。
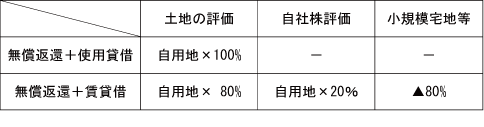
結局、(ア)の使用貸借の場合には、オーナー個人の土地は自用地として100%評価されて小規模宅地の特例優遇はなく相続税の課税がなされます。(イ)賃貸借の場合には、自用地評価額の80%まで評価減がなされ、減額された20%は自社株評価に反映します。さらに、この宅地について、一定の要件を満たせば、400㎡までの部分につき小規模宅地80%減額の特例適用が可能となります。使用貸借と比較すると賃貸借は相続税においてかなり有利なことがわかります。
このように、同族会社への土地の貸付が、使用貸借か賃貸借かによって大きな影響が出ますので、平成27年1月1日の施行を前に、オーナー土地の契約関係を再度確認するのはいかがでしょうか。

※1 改正前は「A+(B×5/3)+(C×2)≦400㎡」の算式により併用が認められています。
A:「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計
B:「特定居住用宅地等」の面積の合計
C:「貸付事業用宅地等」の面積の合計
※2 貸付事業用宅地等を同時に選択する場合には、「(A×200/400)+(B×200/330)+C≦200㎡」の算式により、貸付事業用宅地等の適用面積を算定することになります。
過去のUAPレポート
- レポート検索

