相続税法の「財産の所在」判定と国外財産調書制度~国内財産であっても「国外財産」として申告が必要なもの~
国外財産調書の創設により、5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日までに税務署に提出しなければならないことになっています。
申告しなければならない財産の多くは、相続税法における国外財産と一致していますが、相続税法上、国内財産とされるものでも、国外財産調書に記載しなければならないものがあるので、注意が必要です。
具体的には、居住者が有する下記の(ア)~(ウ)の財産は、相続税法上、国内財産となり、(エ)の信託受益権は、信託財産の所在地が国内であれば国内財産と解されるものですが、国外財産調書制度上では、保証金の受入会社、抵当証券等発行会社、組合、信託会社などの営業所等の所在が国外であれば、「国外財産」として申告しなければなりません(国外送金等調書令10⑥、国外送金等調書規則12③)。
(ア)預託金、委託証拠金、その他の保証金(以下「預託金等」。)
(イ)抵当証券等
(ウ)組合契約出資、匿名組合契約出資等
(エ)(集団投資信託等以外の)信託に関する権利
上記(ア)~(ウ)の財産は、相続税法上、所有者の住所の所在により内外判定をすることが定められています(相法10③)。他方、国内に「住所」を有する個人は居住者となり、国外財産調書制度における申告義務が課されます。したがって、日本に住所がある個人が海外の金融機関などと取引をして年末に(ア)ないし(ウ)の財産を所有していると、これらは相続税法上の国内財産でありながらも、国外財産調書制度の「国外財産」に該当し、申告が必要となります。また、(エ)の信託受益権については、信託財産の所在地で内外判定がなされると解される(相法9の2①⑥)※1ので、信託財産が国内にあれば国内財産に該当しますが、そうであっても、信託会社の営業所等が国外に所在するときには国外財産調書に記載が必要になります。
では、「相続税法上の財産の所在の判定」と「国外財産調書制度の国外財産判定」の異同はどうなっているのでしょうか?
具体的には、下記の【表】に示すとおり、「①動産」から「⑮国債、地方債」までは、相続税法も国外財産調書制度も同じ判定基準により「国外財産」とされます。異なるのは、「⑯その他の財産」の一部で、これらは、相続税法上、信託受益権を除き、「被相続人の住所の所在(=債権者主義※2)」により判定するのに対し、国外財産調書制度では、前述のとおり、「預託金等の受入会社などの営業所等の所在(=債務者主義※3)」で判定します。
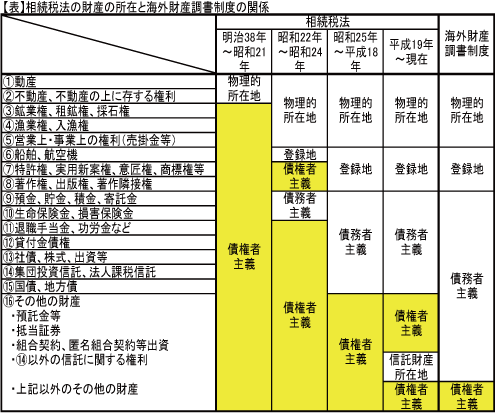
すなわち、「相続税法上の国外財産」と「国外財産調書制度の国外財産」とは、おおむね一致しているのですが、部分的に不一致が生じており、若干の混乱が見られます。
なぜ、このような混乱が起こるのか、それは、国外財産調書の制度趣旨と、相続税法における財産の所在判定の制度趣旨がまったく異なるからです。
国外財産調書は、適切な課税、徴収確保の観点から、国外財産に係る情報の的確な把握を行う趣旨※4で、課税庁が簡単にはつかめない財産の情報を申告により把握しようというものです。
他方、相続税法の財産の所在については、「日本の課税権をどこまで及ぼすのが適切か?」という趣旨で、【表】の推移のとおり、その時々の納税義務者の範囲に対応してその所在が決められています。
制度趣旨が異なるため、財産の所在の両者による判定は必然的に食い違います。にもかかわらず、調書制度では、国外財産該当性の基礎を相続税法においています。その理由は、同制度が財産の所有に関する制度であるため、同じ財産の所有に関する制度である「相続税の財産の所在に関する規定」を基に定めることが適当※5と考えられたからです。
この結果、実務において2つの問題が生じています。すなわち、①相続税法上の国内財産であっても課税当局による情報把握が困難なものが存在する、ということと、②相続税法上の国外財産にも課税当局が容易に情報を把握することが可能なものが存在する、ということです。
前者①には、上述の(ア)~(エ)が該当し、後者②には、「外国株式など相続税法の国外財産となる有価証券等で、国内金融機関において管理されるもの」が該当します。
後者②については、課税当局が把握することが容易な財産であるにもかかわらず、国外財産として申告しなければならず、膨大な手間がかかる過大な義務ではないか、と金融界から不満が出ています。この不満を受けて、金融庁は、平成25年度税制改正要望をだしていますので、近い将来改正される可能性が大きいと考えます。
どうせ変えるなら、「国外財産」調書制度と呼ばず、「把握困難財産」調書制度と名称を変え、対象財産の判定も相続税と切り離して独自のルールに変えてみてはどうでしょうか。

※1 このように解することの詳細は、2012年9月10日発行のUAPレポート「信託受益権の相続税法上の所在場所」参照。
※2 債権者主義とは、その財産の権利者である債権者の住所により、財産の所在を判定することをいいます。
※3 債務者主義とは、その財産の権利者から見ての債務者である、個人、金融機関、法人、受託者などの住所により、財産の所在を判定することをいいます。
※4 吉沢浩二郎ほか『改正税法のすべて』616頁(大蔵財務協会、2012年)
※5 前掲注4・吉沢ほか・619頁
過去のUAPレポート
- レポート検索

