消費税95%ルール改正、一括比例配分方式は有利?不利?
消費税増税が現実味を帯びてきました。法案通り成立すれば消費税率は平成26年4月から8%、平成27年10月から10%となり単純計算で納税額が倍になります。そのためこれまで以上に資金繰りに注意しなければなりません。そして、既に施行されている平成23年6月改正の「95%ルールの適用要件の見直し」も実は資金繰りに影響を与えますので、十分に留意する必要があります。改正によりこれまで課税売上割合が95%以上であることから課税仕入れ等の税額の全額が控除されていた事業者でも、平成24年4月1日以後に開始する課税期間における課税売上が5億円を超える場合には、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかを選んで仕入税額控除額の計算を行うこととされました。そのため、全額控除と比べて必然的に納税額が増加し、資金繰りに影響を与えてくるのです。
資金繰りへの影響を極小化するには、個別対応方式と一括比例配分方式のメリット・デメリットを把握しどちらが有利かを見極めたうえで選択することが求められます。それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。
個別対応方式は、課税仕入れ等を取引ごとに①課税対応仕入れ、②非課税対応仕入れ、③共通対応仕入れに区分経理する必要がありますので、基準となるルールを作成したうえで都度区分を確認しながら処理をしなければならず、事務コストの大幅な増加というデメリットがあります。ただ、一般的に比例配分方式と比べて納税額が少なくなるというメリットがあります。
一括比例配分方式は、課税対応仕入れのうち(1-課税売上割合)分が控除できないため個別対応方式と比べ一般的には納税額が多くなる点と2年継続適用により翌期にも一括比例配分方式を選択しなければならないという点がデメリットとなります。ただし、区分経理をする必要がないため事務コストが増えないというメリットがあります。
これらを比較したときに、課税売上割合が95%以上の場合、納税額だけを見れば一般的には個別対応方式のほうが有利になると考えられます。しかし、非課税対応仕入れが多額になるときは一括比例配分方式の方が有利となるケースがありますので、すぐに結論を出すのは禁物です。
例えば、非課税売上高がほとんどない事業者(課税売上割合99.95%)が居住用建物100,000,000円(別途消費税5,000,000円)を購入し、翌期から家賃等の非課税売上が生ずるような場合です(図1、図2)。
この場合、個別対応方式を選択すると建物に係る消費税5,000,000円は非課税対応仕入れのため控除できません(図1(A))。一方、一括比例配分方式を選択すると課税売上割合99.95%分の4,997,501円が控除できます(図1(B))。結果、個別対応方式よりも控除額合計が大きくなり、一括比例配分方式が4,987,506円だけ有利となります(図1(C))。
翌期は非課税売上高が生じ課税売上割合が減少します(99.95%→96.15%)ので、課税対応仕入れのうち控除できない(1-課税売上割合)分の金額が大きくなりますので個別対応方式を選択していたほうが有利に思われます(図2(D))。しかし、2年通期で見れば、一括比例配分方式の方が有利となっているのです(図1(C)及び図2(D))。
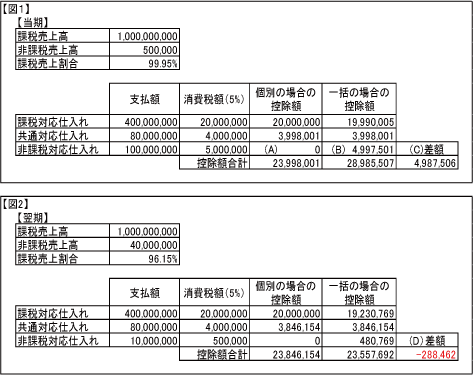
※当期に非課税対応仕入1億円、翌期に非課税売上高4千万円、非課税対応仕入1千万円とした場合。課税売上高、課税対応仕入・共通対応仕入は当期及び翌期ともに同額としています。控除額は概算です。
このような場合は明らかに一括比例配分方式が有利であると当初から判断できますので、事務コストをかけて区分経理をする必要がなく、その分のコストも削減できます。
今回のケースは一例であり、一括比例配分方式が有利か不利かは当期と翌期の課税対応仕入れの額・非課税対応仕入れの額、そして課税売上割合によって大きく異なってきます。そのため、どのような取引が予定されているかを確認し十分な検討をしたうえで選択してください。
過去のUAPレポート
- レポート検索

