税制改正で大法人と中小法人等との格差は拡大。改めて考えたい減資。
平成23年11月30日、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が参議院で可決され、成立しました。平成23年度の税制改正大綱に記載されながら、ねじれ国会の影響もあり法案の成立に至らず継続審議となっていた項目のうち、平成23年11月10日の民主党、自民党、公明党の3党による協議の結果、法人税以外の主要な税目が削除されたため、主に法人税が改正の目玉となっております。法人税についての改正内容を改めて確認すると、特に中小法人等(資本金の額1億円以下の法人等として一定のものをいいます。)以外の法人(ここでは「大法人」といいます。)にとっては大きな影響が予想される内容になっています。
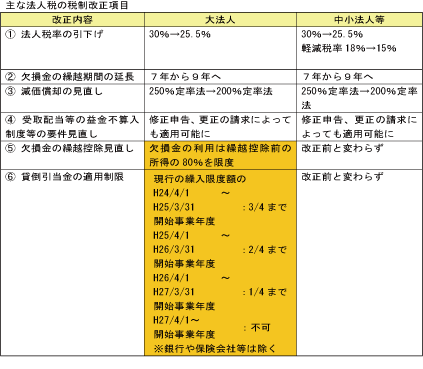
この中で大法人にとって特に影響が大きいと思われるのが⑤、⑥です。⑤は、前期以前に大きな赤字、当期黒字といった場合に、過去の欠損金がいくらあっても利用できる欠損金は所得の8割までに制限されるというもので、2割分の所得に対しては税金を支払わなければならなくなります。⑥は、個別の債権毎に設定する貸倒引当金、債権全体に対して一括に貸倒実績率により設定する貸倒引当金のいずれについても損金への繰入が段階的に制限されるというもので、最終的には貸倒引当金の設定につき一切の損金算入が認められないこととなります。いずれも経常的に利用されることが多い項目だけに目先の税負担の増加につながる改正です。
ここで大法人が上記改正の影響を緩和するために改めて考えてみたいのが、減資による資本金の額の減額です。大法人と中小法人等との境を分けるのは
上記対策を行なった法人では、控除不可能な2割分の所得に対する税額だけ資金の有効活用ができますし、これまで同様に貸倒引当金への繰入額が損金算入できるほか、中小企業等の特例により一括評価金銭債権については一定率を乗じて計算する簡便法をとることも可能になるというメリットがあります。
過去のUAPレポート
- レポート検索

