現物出資受入れ差額の45%控除が認められました
バブルの頃によく行われた事業承継対策で、現物出資を行って含み益を人為的に創出し、その含み益について法人税額等相当額の控除(当時は51%※1 )をして、株式の相続税評価を圧縮する方法(いわゆるA社・B社方式)がありました。
例えば個人甲が、時価100億円のA社株式をB社に現物出資し、B社がその受入価額を1億円と決めると、B社の資産1億円・資本金1億円の会社となりますが、B社が保有するA社株式の時価は100億円なので、結果として99億円の含み益を人工的に作出することができました※2 。
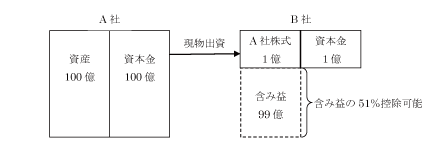
このように、著しく低い価額で現物出資などにより受け入れた株式等にかかる含み益のことを「現物出資受入れ差額」といいます。平成初期において、財産評価基本通達(以下、「評基通」といいます。)による純資産価額の計算上、現物出資受入れ差額については法人税額等相当額の控除が可能でした。この事例のB社の対策当時の相続税評価は、含み益の99億円の51%が控除されることから、100億円-(99億円×51%)=49億51百万円となり、時価100億円のA社株式を直接保有している場合と比較して約半分に圧縮され、相続税負担がその分だけ少なくなっていました。この対策は、非常に有効なものであったため、バブル時に上場株式を保有していた資産家によく利用されていました。
しかし、租税回避の弊害が目に余るため、平成6年に国税庁は、評基通を改正し、経済合理性のない行為により恣意的に創出された現物出資受入れ差額(=含み益)については法人税額等相当額の控除を認めない、という取扱いに変更しました(評基通186-2)。
この評基通の改正により、現物出資を利用した事業承継対策は実行不可能になりました。そのため、この対策を行った人は、組織再編を利用して株式の保有関係を単純にしたり、または、そのまま放って塩漬けにしたりしていました。
ところが、先日、この現物出資受入れ差額について、税務署が法人税額等相当額の控除を認めた事案の存在が、雑誌記事により明らかになりました※3 。
この事案は、平成元年に現物出資により相続税評価額の6%という著しく低い価額で上場株式を受け入れた法人の株式を平成22年に贈与したもので、贈与税の申告につき、いったん法人税額等相当額の控除(=現行の45%による控除。以下、「45%控除」といいます。)をしない申告書を提出しておいて、その後、45%控除をする更正の請求を行い、それが認められたというものです。
現行の通達に反する取扱いがなぜ今回認められたのか、本事案における理由の詳細はよくわからないのですが、先の雑誌記事によると、帳簿等が存在しないためということが理由のようです。
しかし、帳簿等の不存在を理由とすると、法定期間を超えて帳簿等を保存している会社の相続税評価が高くなり、さっさと廃棄してしまった会社の評価が安くなります。結果として真面目な納税者が損をすることとなり、公平の観点から非常に問題です。
真の理由は、現物出資受入れ差額について「永久に」45%控除を認めない、という現行の取扱いには様々な問題点があるからだと思われます。
一つは帳簿等の保存期間との関連で、長期にわたり現物出資受入れ差額が把握できるのかという実務的な問題点と、もう一つはそもそも現物出資当時の人工的な含み益が20年後の現在も存在しているといえるのかという理論的な問題点です。
後者の理論的な問題点について、株式の含み益に議論を絞って考えてみます。バブル当時の株価は現在では激減している※4 ため、当時の含み益はもはや消滅しているといえます。たとえまだ消滅していないとしても、その当初の含み益は、その後の会社の投資や経営努力によって自然発生的に生じた含み益に置き換わっていると考えることもできます。つまり、現物出資当時の人工的な含み益は消滅しているか、その後の自然発生的な含み益に置き換わっているか、または、両者が混在して区別がつかなくなっているかのどれかです。
このような実態があるのにもかかわらず、現行の評基通186-2の45%控除制限規定は、過去のどの時点の現物出資であっても無制限に適用されますが、この取扱いはあまり合理的だとはいえません。前述のとおり、長期間経過後には、当初の人工的な含み益がどのくらい残っているかは判断のしようがないため、この制限規定は期間を決めて適用すべきであり、具体的には、現物出資から3年間、または、長くても法人税法の帳簿保存期間である7年間に適用を制限するような評基通の改正が望まれます。
評基通の改正はともかく、バブルの頃に実行した現物出資などで45%控除ができなかった方の相続や贈与では、今後有利な申告ができる可能性が十分ありますので、是非検討されてみてはいかがでしょうか。

※1 控除割合は課税時期によって異なりますが、平成2年4月1日以降平成10年3月31日までは51%であったため、本稿は51%で説明しています。なお、現在の控除割合は45%となっていますが、その詳細については2010年8月2日のUAPレポート「納税者有利に改正された45%控除~純資産価額方式における法人税等相当額~」を参照して下さい。
※2 当時の法人税法では、現物出資財産の受入価額は時価以下であれば合法であったため、低い価額の受入記帳が可能でしたが、現在では時価で取得価額を付すこととされているためこのような受入記帳はできません。
※3 「帳簿類不存在で45%控除規制が形骸化」T&AマスターNo.423・4~7頁(2011.11.17号)
※4 日経平均株価でバブル当時は3万円以上だったものが現在では8~9千円にまで落ち込んでいます。
過去のUAPレポート
- レポート検索

